こんにちは
メープルです。
もし、認知症の方が「施設」ではなく「日常のまち」の中で、
自分らしく暮らせたら
そんな理想を、現実にしている場所があります。
それが、オランダ・ホグウェイ村(Hogeweyk)です。
今回は、世界中の注目を集める
ユニークな認知症ケアコミュニティの魅力を、
深掘りしてお伝えします。
■ ホグウェイ村とは?
ホグウェイ村は、オランダのアムステルダム近郊にある「認知症の人のための村」。
外見は普通の小さな街。
スーパー、美容院、カフェ、郵便局、広場、住宅が並び、
人々が穏やかに暮らしています。
でも、住民は全員が中〜重度の認知症の人たち。
そして、スタッフは「ケアをしている人」ではなく、
「隣人として日常を一緒に過ごす人」として存在しているのです。
■ 魅力1:閉じ込めない「自由な空間設計」
ホグウェイ村には塀がありますが、
それは「閉じ込めるため」ではなく、
「安心して自由に歩けるため」。
24時間開放された街の中で、住民は好きな時間に散歩をしたり、
カフェに行ったり、買い物を楽しんだりできます。
転倒や迷子の心配がないように、安全性が徹底されている設計の中で、
本人の意思や行動が尊重されているのが大きな特徴です。
■ 魅力2:「暮らし」が治療になるという発想
ホグウェイでは、「治す」より「その人らしく暮らす」ことが最優先。
医療や介護はあくまでも裏方で、
表には本人が心地よく生きられる生活が用意されています。
住民は7〜8人ごとの小規模な家に分かれて暮らし、
スタイル(文化的背景)に応じて家具や料理、
音楽も変えるというこだわりよう。
たとえば、農村出身の人には昔ながらの木造の家、
都会育ちの人にはモダンなインテリア。
「自分の居場所」として感じられる空間は、
認知症の人の混乱や不安を和らげ、
穏やかさを取り戻すと言われています。
■ 魅力3:スタッフは「ケアの人」ではなく「生活の仲間」
スタッフは医療従事者や介護士でありながら、
住民と一緒にご飯を作り、会話をし、時には笑って踊る
そんな「対等な関係」を大切にしています。
また、衣装や役割にも工夫があり、
「白衣の医者」ではなく「近所のお兄さん」や「店員さん」として接することで、
住民の心を和らげているのです。
■ 魅力4:コストより“価値”を追求する姿勢
ホグウェイ村の費用は、
実は一般的な老人ホームとほぼ同じ水準。
運営は一部公的資金や助成を活用しながら、
「日常生活にかかるコストを最優先」に設計されています。
つまり、高級な施設ではなく、
「思いのある設計」が人を幸せにするという哲学がそこにあります。
■ 日本へのヒント:認知症ケアのパラダイムシフト
ホグウェイ村は、私たちに問いかけます。
• 認知症の人にとって「安全」とは何か?
• 日常生活の中で、どんな「自由」や「尊厳」が守られるべきか?
• ケアとは、管理することではなく、「その人らしさを支えること」ではないか?
日本でも、ユマニチュードや地域包括ケアなど
「寄り添う介護」の動きは進んでいますが、
ホグウェイ村のような大胆な発想の転換にはまだ距離があります。
けれども、今後高齢化が進む日本にとって、
「ホグウェイ的な考え方」はきっと希望のヒントになるはずです。
まとめ
ホグウェイ村が教えてくれるのは、
「ケア」ではなく「生活」という視点。
「守る」ではなく、「共に暮らす」という選択。
そこには、認知症を持つ人も、支える人も、
どちらも笑顔になれる未来が広がっています。

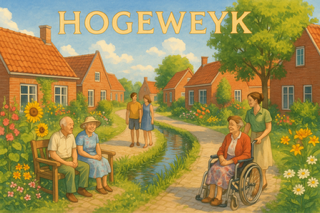


コメント